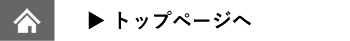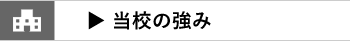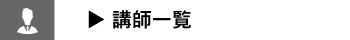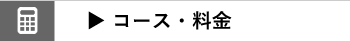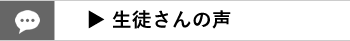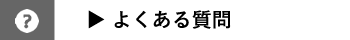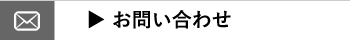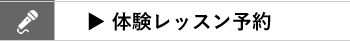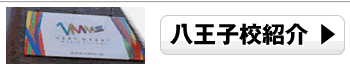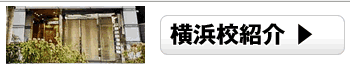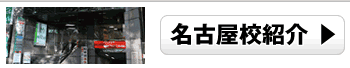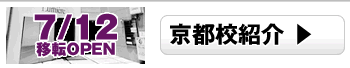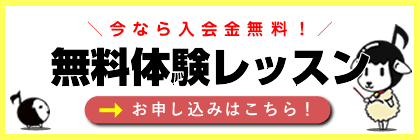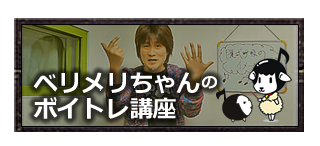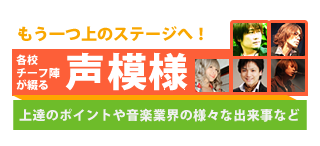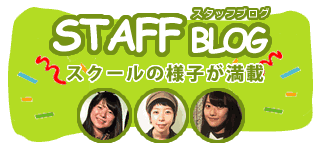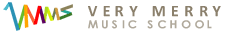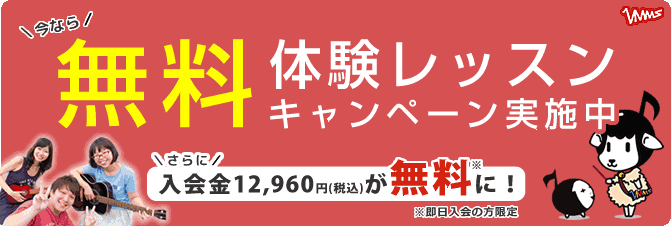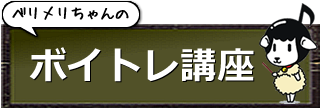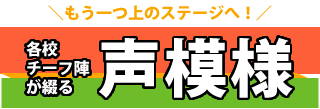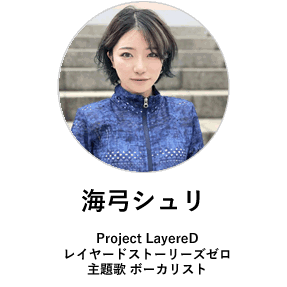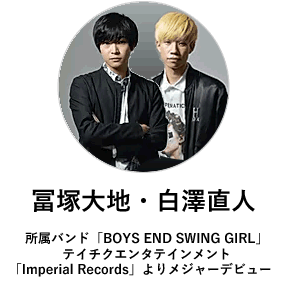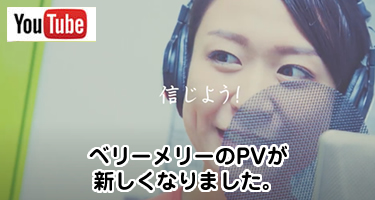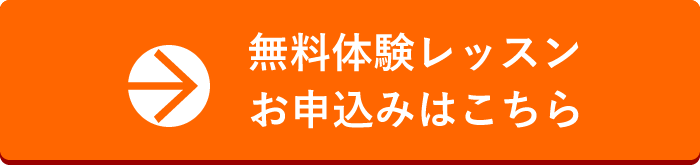ボイストレーナーは、それぞれの経験やレッスンの中でたくさんの“気づき”を得ています。
これらは生徒さんに伝える言葉として、時にはエネルギーを持った言霊のように使われています。
今回のコラムでは、ボイストレーナー本田が20年の経験の中で見つけた、歌や表現に役立つ気づきをまとめてみました。
ちなみに、本人はこれを「名言」と呼んでいます(笑)でも、読んだ皆さんがどう感じるかはお任せです。
これまで書いてきた「声模様」と重なる部分もあるかもしれませんが、新しい気持ちで読んでいただけたら嬉しいです。
皆さんのこれからの歌に、少しでも役立ちますように。
〈気づき:心構えとして〉

根拠のない自信と根拠のある自信を持とう
「自分には何か特別な才能があるかもしれない」という根拠のない自信と、「練習したんだからできるはず」という根拠のある自信の両方が、自分の歌を支えてくれます。
生徒さんにもよく伝えるのは、根拠のない自信は挑戦の原動力になり、根拠のある自信は安定感を生むということ。
例えば、本番で緊張しても「やってきたんだから大丈夫」という思いが力をくれます。
音楽性はたくさん音楽に触れると高まる
さまざまなジャンルの音楽を聴いたり演奏したりすることで、表現力や音楽の幅は自然に広がります。
一曲にこだわるだけでなく、異なるリズムやフレーズを経験することが、柔軟な表現力につながります。
歌は一人で演奏する楽団のようなもの
歌うとき、あなたは一人で演奏者・楽器・指揮者の役割を兼ねています。
- 演奏者:横隔膜やインナーマッスルで息を作るお腹の支え
- 楽器:声帯・口腔・鼻腔など、息が当たって音を出す部分
- 指揮者:これまでの人生で培った音楽性をもとに、歌声をプロデュースするイマジネーション
この視点を持つと、ただ歌うだけでなく、自分の声を総合的にコントロールする意識が生まれます。
歌が上達すると会話でも言葉が伝わりやすくなる
歌の表現力は、日常の会話にも反映されます。
声のトーンやニュアンスの使い分けができると、相手の心に届くコミュニケーションが可能に。
生徒さんには「歌の練習は、歌だけでなく自分の話し方も変える」と伝えています。
〈気づき:歌上手に役立つ〉

英語のニュアンスがあると歌声にも良いニュアンスが生まれる
英語のアクセントやフィーリングを取り入れると、柔らかく流れる表現が可能になります。
日本語の歌でも、強弱やイントネーションの幅を広げるために、英語の感覚を応用することは大きなヒントになります。
たくさんの人と音を合わせる(アンサンブル)と音感・リズム感が育つ
バンドやオーケストラなど、複数人で音を合わせることで、人の音を聞き分ける力やリズム感が自然に育ちます。
誰が何をやっているのか把握する力は、自分の演奏力を高めるだけでなく、音楽的なコミュニケーション能力にもつながります。
喜怒哀楽を深めることは歌の表現に直結する
感情の幅を増やすことで、歌声の表現力も豊かになります。
明るい声、切ない声、力強い声など、感情のニュアンスを意識するだけで、歌が生き生きとしてきます。
メトロノームと友達になろう
リズムの安定は、歌の土台になります。
メトロノームと何度もアンサンブルすることで、自分のリズム感も磨かれ、迷いのない演奏ができるようになります。
腹話術ができると基礎力がアップする
口を大きく開けずに母音や子音を作る練習は、響きの最小構成を理解するトレーニングになります。
声の芯や息の使い方が自然に身につき、効率的な発声につながります。
インナーマッスルの持久力は安定した歌声の特効薬
下半身の支えは息の流れを安定させ、歌声の根幹を支えます。
くしゃみや咳の息を擬似的に使った練習で、インナーマッスルの存在を実感しながら活用できます。
まとめ
読んでみていかがでしたか?
直ぐに思い出せないだけで、まだまだ沢山の“名言”(本当に自分で言うな〜笑)を吐いてきました。
これは長く音楽と関わってきた証だと感じています。
何より大切なのは、これらの気づきを自分の実感として身につけること。
上記の内容をヒントに、ぜひご自身の歌や表現に活かしてみてください。
≫ 無料体験レッスンはこちら
八王子校・横浜校チーフ
本田 ‘POM’ 孝信
この記事を書いた人
レッスン中も得意の駄洒落を連発する癒し系講師。所属するバンドcan/goo(アニソン中心)はキングスーパーライブ2018(東京ドーム)にて水樹奈々、宮野真守など豪華アニソンシンガー等と共演♪作詞作曲家としての視点も持つ。