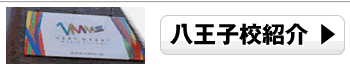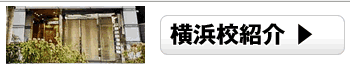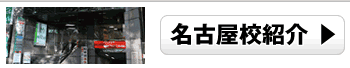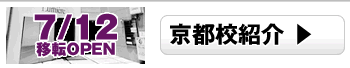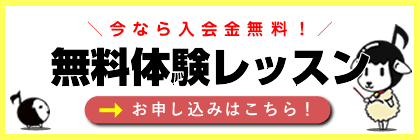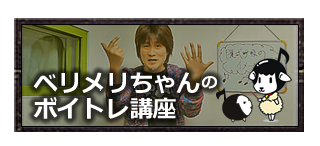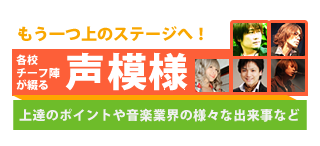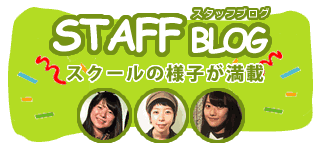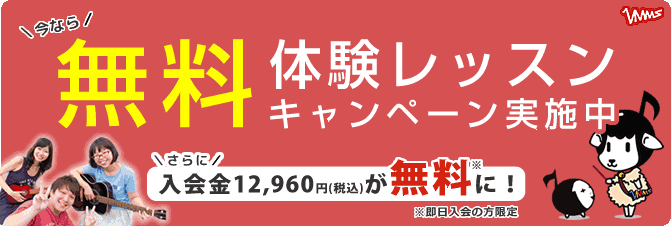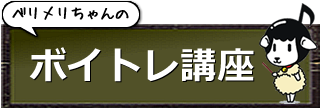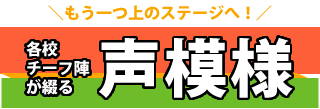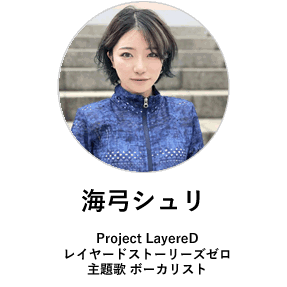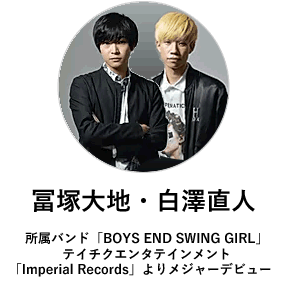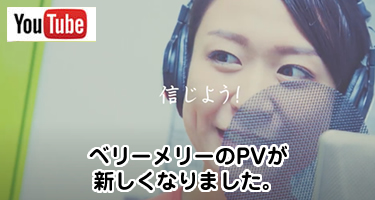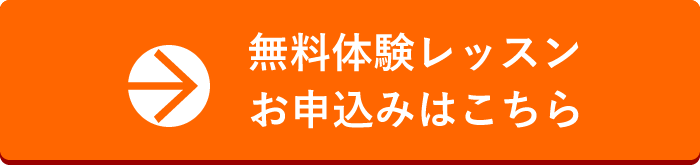歌がうまくなりたい。
声をもっと響かせたい。
自分らしい表現力を身につけたい——。
そう思ったとき、技術的な練習はもちろん大切ですが、実は“歌心(うたごころ)”のような内面の部分も、歌の説得力に大きく関わってきます。
今回は少し視点を変えて、古典文学「百人一首」の世界から現代のボイトレにも活かせる“表現のヒント”を探ってみたいと思います。
和歌って、ただの古文?いえいえ。
そこには、短い言葉に込められた深い感情や情景が詰まっていて、歌を“伝える”ためのヒントがぎっしり詰まっているんです。
少し意外なアプローチですが、きっと今の歌にもつながる気づきがあるはずです。
ボイトレに効くのは、古典の世界?
名作ドラマ『ちはやふる-めぐり-』——皆さんはご覧になったことありますか?
“かるた”に青春をかける高校生を演じた上白石萌音さんが、時を経て今作では教師となり、再び「かるた部」を導くという展開になっています。
実は前作は観ていなかったのですが、今回の作品で特に印象的だったのが、上白石萌音さんが詠む百人一首のシーン。
歌手としても評価の高い彼女の声で詠まれる短歌は、まさに響きそのもので、胸に迫るものがありました。
これまで「短歌って“歌”って言うけど、実際はメロディないし…」なんて思っていた自分ですが、短いフレーズの中にしっかりと起承転結があり、その情緒が部屋中に響き渡るさまは、現代の歌と何ら変わらない表現力があるのではと気づかされたのです。
短歌に込められた筆者の想い

百人一首は、およそ800年前に藤原定家が編んだ和歌集です。
「新古今和歌集」なども有名ですが、百人一首は5・7・5・7・7の計31音という決められた文字数で構成され、季節・恋・旅・別れなどのテーマに分かれています。
限られた言葉数の中で情景や心情を描くためには、読んだ人の想像力が必要になります。「行間を読む」という感覚はまさにこれですよね。
日本語の奥ゆかしさ、比喩や余白の美学は、説明しすぎず、受け手の感性を引き出します。その結果、誰かの心に長く残る「共感」が生まれる——。
この感覚、現代のポップスにも通じるものがあると感じませんか?
最近のヒットソングには「応援歌」のようなメッセージ性の強いものも多く、Mrs. GREEN APPLEさんの楽曲などはその代表格です。きっと、昔の短歌にも“推し”の詠み手がいて、共感する気持ちから自然とファンが生まれていたのではと、ふと思ってしまいます。
短歌もポップスも、5分でも31文字でも、心に訴えかけるものがあれば、それは同じ「歌心」。強い想い、儚い想い、切ない想い……そこにはいつも“共感”があるのだと思います。
声の響きに秘められた人生の機微

百人一首の中に、こんな歌があります。
やはり短歌は縦書きで見ると、より心に迫ってきますね。
この歌は、急流が岩にぶつかって流れが分かれても、やがてまたひとつに戻るという自然の情景を、人の心に重ねています。
恋人と今は別れてしまったけれど、いつかまた出会える——そんな希望を秘めた切ない想い。そこに「滝」という言葉が使われていることで、流れの強さや激しさまで感じられます。
こうした短歌は、競技かるたでは「読手(どくしゅ)」が切々と詠み上げていきます。ドラマ『ちはやふる』の中で上白石萌音さんが言っていたように、「かるたに勝つことも大事だけれど、一つひとつの句を理解していることがもっと大切」なのだと。
これは歌にも通じます。
歌が多くの人の心に残るのは、その中に“伝えたい気持ち”がしっかり込められているから。メロディーや歌詞だけではなく、歌う人の「想い」が声に乗ることで、初めて本当の“響き”になるのだと思います。
笑顔で歌えば、明るく軽やかな響きに。
涙を流しながら歌えば、切なく揺れる声に。
悔しさをにじませれば、絞り出すような力強さに——
その人の人生経験や気持ちが、自然と声のニュアンスに現れてくるのです。
短歌のロングトーンとメロディーの流れ

短歌を聴いていて感じたのは、語尾が自然とロングトーンになること。フレーズごとに丁寧に言葉を紡ぎ、余韻を残すことで“詠嘆(えいたん)”の深みが生まれています。
一息で紡がれる5音・7音は、ある意味で短いメロディーのようなもの。息の使い方、言葉の区切り方、間の取り方——RAPにも通じる部分があります。
読手によって語尾の仕上げ方も異なり、ビブラートをかけたり、息を混ぜたりと表現は多彩。いろんな方の音源を聴いてみましたが、本当に好みが分かれると思いました。
男性・女性どちらもいらっしゃって、それぞれの一番心地よい音域で詠まれていますが、全体的には「ド」と「ソ」の5度くらいの音域で安定しているように感じます。
今の音楽もそうですが、音程やリズムだけが良くても“響かない”ことってありますよね。短歌の読手の中には、技術よりも“想い”を伝えることに長けた方がいて、それが本当に心に沁みました。
まとめ
歌のフレーズは、基本的にブレスから次のブレスまでロングトーン。音程が動いても、息の流れは一筆書きです。
ぜひ一度、短歌を詠むように歌ってみてください。難しいことは考えず、真似事で構いません。
そこには、ロングトーンの深さ、語尾のたおやかさ、アクセントの強さ、柔らかさと力強さ……歌に必要な“表現のエッセンス”が、シンプルに存在しています。
そして何より、詠む人(歌う人)によって聞こえてくる“色”が違うのです。声から情景が浮かび、気持ちが伝わる——それが“歌心”だと思います。
歌は、時代を越えて受け継がれる素晴らしい表現手段です。もちろん、何気ない鼻歌にもその時の自分の感情がこもっているはずです。
誰かに想いを伝えたくて歌詞を書く人もいれば、ただ大好きな曲を上手に歌えるようになりたい人もいる。
どんな動機でも構いません。ぜひ、「あなたらしい唄声」を大切にしてみてください。
—
ベリーメリーミュージックスクール 八王子校・横浜校 チーフ
本田’POM’孝信
この記事を書いた人
レッスン中も得意の駄洒落を連発する癒し系講師。所属するバンドcan/goo(アニソン中心)はキングスーパーライブ2018(東京ドーム)にて水樹奈々、宮野真守など豪華アニソンシンガー等と共演♪作詞作曲家としての視点も持つ。