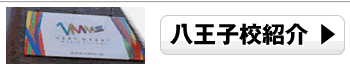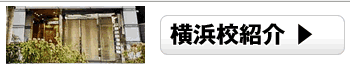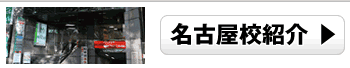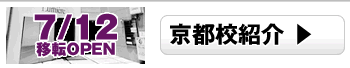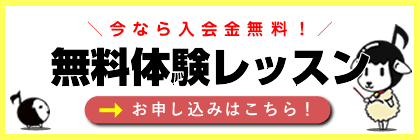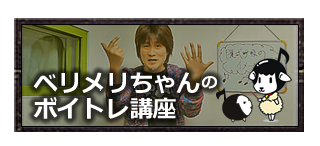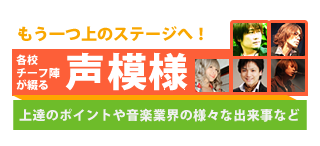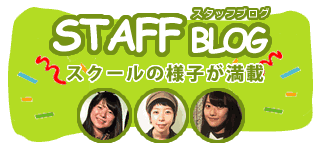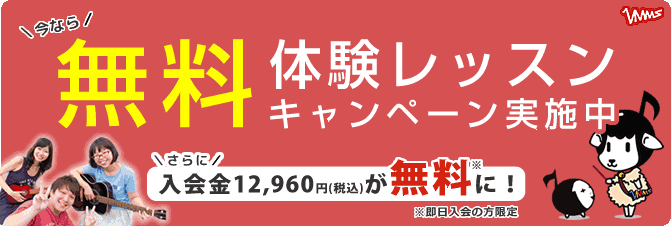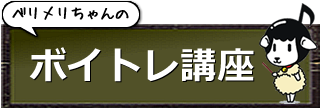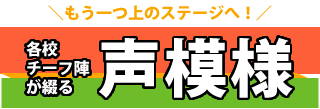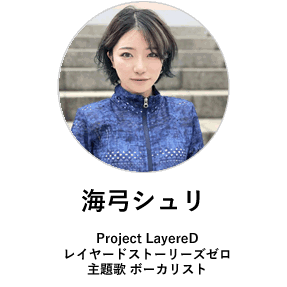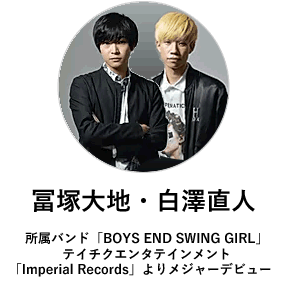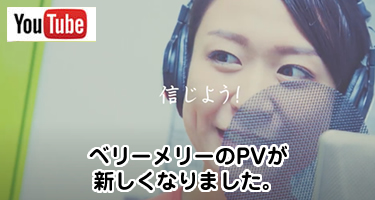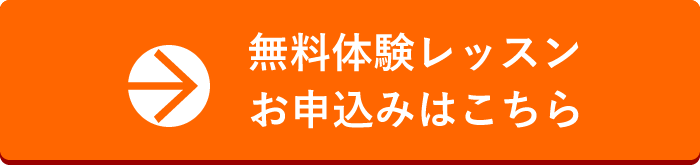「歌うとき、どんな筋肉を使ってるんだろう?」
「腹式呼吸って聞くけど、結局どこの力を入れたらいいの?」
歌声は、実は“筋肉の連動”でできています。
横隔膜や喉の周り、表情筋まで、体中のさまざまな筋肉が協力し合って声を作り上げています。
ただし今回お伝えするのは、解剖学的に正確な「理論」ではなく、ボーカリスト・ボイストレーナーとして20年以上レッスンを重ねる中で体感してきた“感覚的な働き”です。
人によって感じ方は異なりますが、「こう意識すると声が出しやすい」「この感覚を掴むと響きが良くなる」という、いわば“身体と声のリアルな関係”をお話しします。
声を出す時に働く筋肉の感覚
声を出すときには横隔膜(インナーマッスル)や輪状甲状筋など、いくつもの筋肉が連動しています。
医学的には、「呼吸筋・喉頭筋・共鳴筋群」などの分類で説明されることもありますが、実際に歌う時はそんなに細かく意識することはありません。
ボーカリストが感じるのは、もっとシンプルな“働き”です。
たとえば、息を吸う時にお腹がふくらみ、吐く時に内側から押し出すような感覚。声を出すときには、喉だけでなく下半身や背中、体幹の奥がじんわり動くような感覚が伴います。
この「全身のつながり」を意識することが、良い歌声を作る第一歩です。
歌っているとき…
✅ 下腹部がしっかり動いているか
✅ 肩や首に余計な力が入っていないか
✅ 息がスムーズに流れているか
この3つを確認してみましょう。
特に、喉だけで頑張ろうとしないことが重要です。喉は音を作る“出口”であって、力を生み出す“エンジン”ではありません。力の源は体幹、特に下腹部と背中の深い部分にあります。
ボイストレーナーとして多くの生徒を見てきて感じるのは、上半身に力を入れすぎる人ほど音が詰まり、息が浅くなるということ。逆に、下半身から息を支えられる人ほど、声が軽やかで響きが遠くまで届きます。
「喉を開く」「支える」という言葉はよく聞きますが、実際は全身の筋肉バランスを取る感覚のこと。
それを掴むだけで、歌声がぐっと安定します。
横隔膜(インナーマッスル)の力の入れ方

咳やくしゃみの時、横隔膜が痙攣することで勢いよく息が流れます。この動きは、発声においても非常に参考になります。
オペラ歌手が「へクション」ではなく「ペプシン」と言い換えてくしゃみを逃がすのは、喉への負担を減らすため。「ク」は喉を締めますが、「プ」は唇で息を逃がせるため、声帯を傷めにくいのです。
この“息の抜け感”を意識しながら、横隔膜を震わせるように息を送ると、声の起点を喉ではなく下腹部に置く感覚がつかめます。上半身に力みがなく、自然に声帯が息を受け止める状態です。
また、空手の「気合い」やボクシングの「ひねり」のように、体幹から生まれる力を活かすこともポイント。丹田を意識して下腹部に力を入れると、横隔膜が下がり、内臓を圧迫して肺を下から押し上げます。
歌はパンチのような一瞬ではなく、持続的なコントロールが必要です。ベルトを少しきつめに巻いてお腹を膨らませるように力を入れ、「シー」と細く長く息を吐く練習をしてみましょう。
腹筋運動をしながらでもOKです。ただし、上半身に力が入りすぎると逆効果。あくまで「お腹で支えて、上はリラックス」が基本です。
喉周りの力の入れ方

息が整ったら、今度は“受け止める側”の喉の筋肉。声帯自体は筋肉ではなく、周囲の筋肉が協力してその形や張りを変えています。
大まかには、地声・ファルセット・ミックスボイスなどのポジションがあります。それぞれをコントロールするには、喉仏の位置や首の筋肉の使い方がカギ。
👄喉まわりをリラックスさせたまま喉仏を軽く持ち上げる → ファルセット
👄首の筋肉を太く広げながら喉仏を上げる → 地声のまま高音
喉を締める方向に力を入れると、ほぼ確実に詰まります。
「首を太く」「喉を広く」という意識を持つだけで、音の抜けが大きく変わります。舌根を下げて口の中を広げると、より安定します。
胸に力を入れすぎると声が硬くなるので、息の支えは常に下腹部から。指を軽く噛んで音階を上げると、余計な力を抜く練習にもなります。
表情筋の力の入れ方

音は「力を入れた場所」に響きます。喉に力を入れれば喉声に、顔の上部(眉やこめかみ)に意識を置けば明るい響きに変わります。
「う」や「お」を発声する時、口角を寄せて口をすぼめると、音が前方に集まってきます。普段の会話ではあまり使わない筋肉なので、衰えがちな部分です。「うぃう」「うぉう」などの発声練習で、口周りの筋肉をしっかり動かしましょう。
また、表情の違いで声色が変わることも大切なポイントです。
🎤 笑顔で歌う→明るく軽いトーン
🎤 悲しい表情→柔らかく深い響き
🎤 怒りの表情→声にハリと圧が出る
つまり、感情表現そのものが表情筋の使い方と直結しています。喜怒哀楽を自在に表現できることが、歌声の表現力を豊かにします。
鏡の前でいろんな表情を作りながら発声する練習は、実はとても有効。顔全体が柔らかく動くことで、音の響きも自然に広がっていきます。
まとめ
横隔膜や下半身の筋肉は“息のコントロール”を、喉の筋肉は“声のポジション”を、表情筋は“声色と表現力”を担っています。
どの筋肉も使わなければ衰えます。プロのシンガーでも、しばらく歌わないと音程が不安定になったり、声の伸びがなくなるものです。
ボイトレやライブ、カラオケなどで日常的に声を出すことが、何よりのトレーニング。
ただし、間違った使い方でクセをつけてしまうと逆効果にもなるため、ボイストレーナーの指導のもとで練習するのがおすすめです。
正しい身体の使い方を覚えて、気持ちよく、自由に歌えるように。
ベリーメリーミュージックスクールでお待ちしています。
≫ 無料体験レッスンはこちら
八王子校・横浜校チーフ 本田‘POM’孝信
この記事を書いた人

レッスン中も得意の駄洒落を連発する癒し系講師。所属するバンドcan/goo(アニソン中心)はキングスーパーライブ2018(東京ドーム)にて水樹奈々、宮野真守など豪華アニソンシンガー等と共演♪作詞作曲家としての視点も持つ。