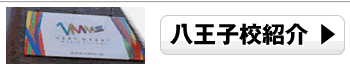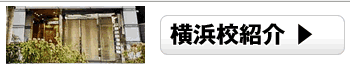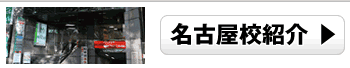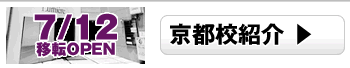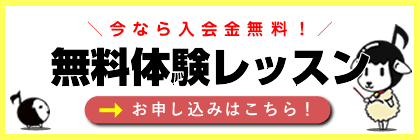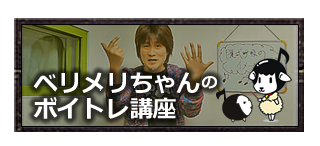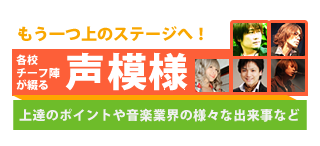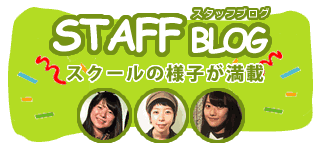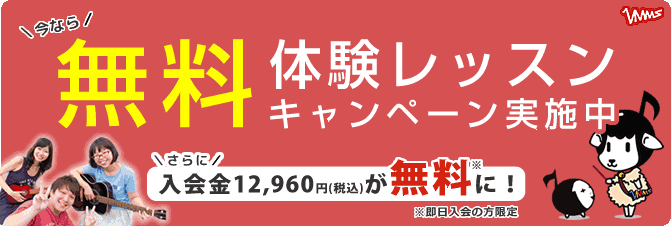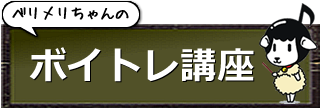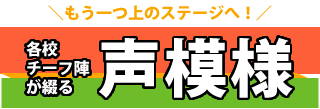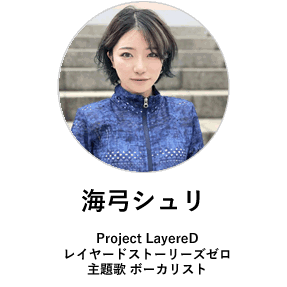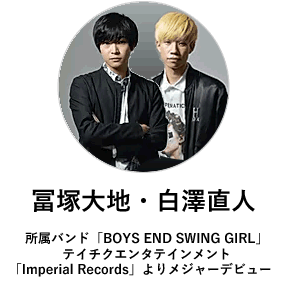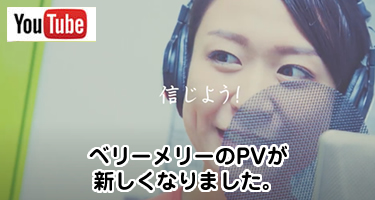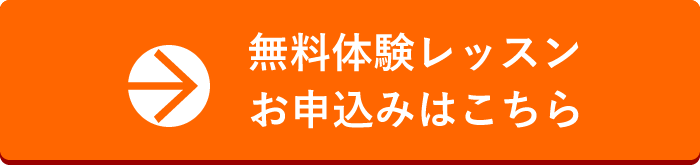歌が上手い人を見ると「生まれつきの才能かな?」と思いがちですが、実はそうではありません。
声は筋肉や体の使い方、そしてちょっとした意識の違いで大きく変化します。
大切なのは、自分の声の「自然な響き」と「個性」を知り、それをどう生かしていくか。
この記事では、声を“自分だけの楽器”としてとらえ、響きを育てるための考え方を紹介します。
「声」は「世界にひとつの楽器」
私たちは誰もが、自分だけの「楽器=声」を持っています。
同じ声はひとつとして存在しません。似た響きを持つ「系統」はあっても、根本的には全員違う楽器を鳴らしているようなものです。
さらに人生の中で触れてきたもの――親や友人、食べ物、部活、音楽、趣味など――が、少しずつ声の個性を形づくっています。話し方や歌い方、体の使い方にまで影響を与えているんです。
ボイストレーナーは、まずその人が持つ「自然な鳴り=声の響き」を引き出し、同時に身についてきた「癖」を見極めます。
癖をすべて取り除くのではなく、どの程度残すかを見極めながら、その人の個性を最大限に生かすのも大切な役割です。
自然な声の鳴りは「脱力」から

楽器は、弾いたり吹いたりして力を加えると響きが生まれます。声も同じで、声帯(弦)と気管(管)が振動し、口腔や鼻腔、頭蓋骨を通して響きを広げています。
ただし、力が入りすぎると響きは失われます。顎や胸が固まると、せっかくの声の振動が小さくなってしまうのです。
一番自然な声は「力を抜いて息を流す」ことで生まれます。風鈴をそっと鳴らすように、声も余計な力を抜くことが大切なんですね。
個性は「自然な響き+癖」のバランス
声の個性は、生まれ持った体のつくり(口の大きさ、鼻や首の形など)と、環境や経験から身についた「癖」との調和で生まれます。
例えば…
- 高音に憧れて無理に喉を締めて歌うことでついた「締め癖」
- 下顎に力が入ってしまう「喉声」
- 胸に力を入れた硬い声
こうした癖は一見マイナスですが、完全に取り去ってしまうと“面白みのない声”になることも。
実際に、優里さんは下顎を前に出して高音を歌うことがありますし↓↓↓
玉置浩二さんも普段は太く柔らかな声ですが、ときに「喉声」で表現されることがあります↓↓↓
大切なのは、自分の「自然な声」と「癖」をどう調和させるか。そこに、その人だけの表現力と魅力が生まれるのです。
自分の声を客観的に知るメリット

「自分の声が好きじゃない」と感じる人は少なくありません。生徒さんからもよく聞く言葉です。
ですが、大事なのは“好き嫌い”ではなく、“客観的に自分がどんな声を持っているか”を知ること。
自分のナチュラルな響きと癖を理解できれば、曲選びや表現の幅がぐっと広がります。
ライブ映像やレコーディング音源を見返すことも、自分の声を知る大きな助けになります。
まとめ
オーディションでは「歌の上手さ」以上に「声の良さ」が評価されることが多いものです。
癖のある声でも自然に響いていれば、人の心に届き、何度も聴きたくなる存在になります。
そして何より、自分の声で歌って「楽しい」「切ない」と感じられること。
それこそが、歌を続ける一番の喜びではないでしょうか。
あなたも、自分だけの楽器=声をもっと知り、もっと好きになってください。
八王子校・横浜校チーフ講師
本田 “POM” 孝信
🎤 ベリーメリーミュージックスクールでは、あなたの声の魅力を引き出すレッスンを行っています。
まずは気軽に、無料体験レッスンで「自分の楽器=声」を確かめてみませんか?
🔗 無料体験レッスンについて
この記事を書いた人

レッスン中も得意の駄洒落を連発する癒し系講師。所属するバンドcan/goo(アニソン中心)はキングスーパーライブ2018(東京ドーム)にて水樹奈々、宮野真守など豪華アニソンシンガー等と共演♪作詞作曲家としての視点も持つ。