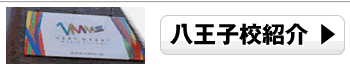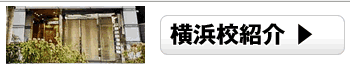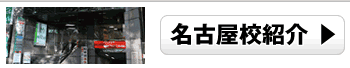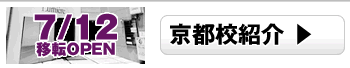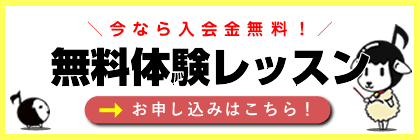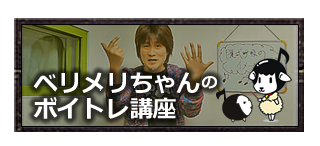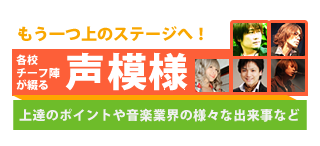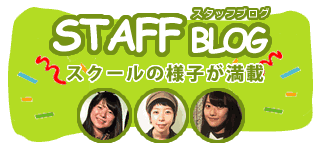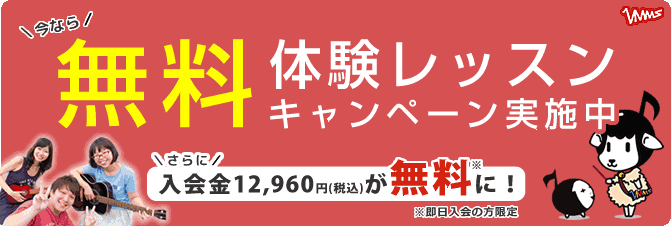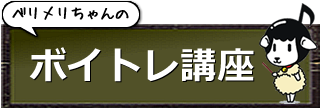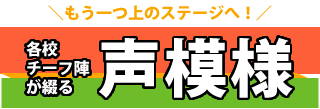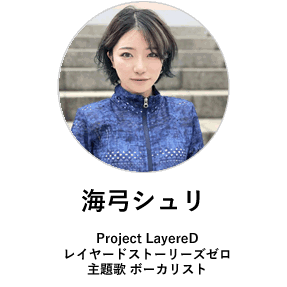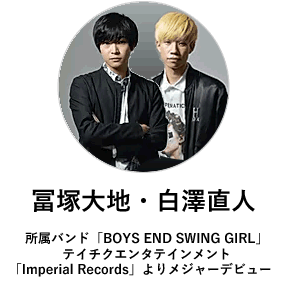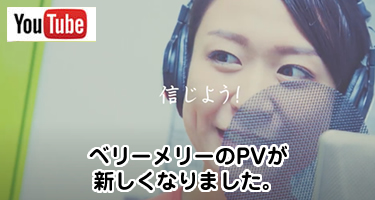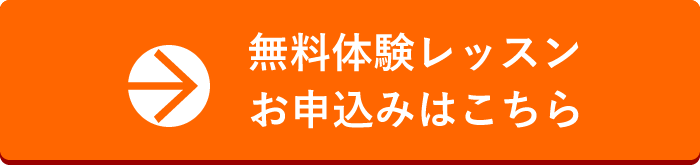新しい曲を練習するとき、「どこから手をつけたらいいのか分からない」と迷うことはありませんか?
ボーカルスクールに通っている方も、自己流で練習している方も、“練習の視点” をあらかじめ整理しておくと、理解度や上達スピードがぐんと上がります。
ここでは、私が講師としておすすめしたい、1曲を4ステップで仕上げるためのトレーニングメニューを紹介します。
レッスンを受けている方は、この考え方を頭に置くことで、レッスン内の吸収が深まり、「ここを重点的にやってほしい」とリクエストする際の材料にもなります。自己流で頑張っている方も、ぜひ参考にしてみてください。
やり方に迷ったら、いつでも ベリーメリーミュージックスクール に相談してくださいね。
ステップ1:曲と自分の相性を分析する

まずは「情報収集」と「自己分析」からスタート。曲を“素材”として観察しましょう。
- 曲中の最高音は地声か裏声か?
- その高さを理想の声質で安定して出せるか?
- 最高音やその近辺がどのくらい登場するか(頻度・長さ)
- 最低音の声質はどうか?
特に④は見落としがち。低い音を無意識に扱うと、フレーズが平坦になりやすく、音程も不安定に。「最低音をウィスパー寄りにして表現を作ろう」など、あえて設計を立てることで、抑揚のある歌い方ができます。
ステップ2:課題を踏まえて実践トレーニング
分析したポイントを、声に落とし込むステップです。以下の4つのポイントに沿って曲を解析し、順を追って練習していきます。すべてを一度に意識するのは難しいので、一つずつ丁寧にこなせるよう意識してみましょう↓↓↓
1.最高音の扱い
- 余裕があるなら → 曲のキーを変えながら「熱く」「クールに」など印象を試す
- ちょうど良いなら → そのまま声色の研究へ
- 無理があるなら → 一度キーを下げ、安定させた後で少しずつ戻す。並行して音域を広げる発声練習を。
2.声色と母音
高さが出せるだけでは不十分。ロック曲で温度のない声は寂しいし、ボサノバで力強すぎてもミスマッチ。また、同じ音でも母音によって出しやすさは違います。
歌詞を確認し、最高音周辺にどの母音があるかを把握し、その母音での発声を重点練習しましょう。
3.ブレスとスタミナ
単発練習で出せても、曲中では出せないことがあります。直前のブレス量や長さが原因かも。
拍を意識しながら、実際のフレーズと同じ長さ・回数で息を吸い、発声する「フレーズ発声練習」を取り入れると効果的です。
4.最低音の扱い
弱い声の加減を丁寧に確認。ピッチが浮かないよう注意しつつ、ウィスパー、ビブラート、短く切る…など、表現の幅を試しましょう。
“弱さ”があってこそ“強さ”が際立つのです。
ステップ3:1コーラスに絞って歌い込む

発声練習やフレーズごとの練習でうまくできていたことも、いざ通して歌うと難しく感じる場合があります。その原因を見つけたり、改善のヒントを得たりする時間にしてください。
また、1フレーズ単体では良かった抑揚や表現が、前後とのつながりを考えると違和感があったり、スタミナ的に無理が出てきたりすることもあります。
「とりあえず全部歌いたい!」という気持ちは少し我慢して、まずは1番をしっかり安定させることを目標に取り組んでみましょう。
ステップ4:録音して客観視する

仕上げはレコーディングです。1コーラスだけ録音して、自分の声を客観的に聴きチェックします。
🎤最高音・最低音の質は?
🎤声色はイメージ通り?
🎤弱さや抑揚は伝わっているか?
録音を聴くと、新しい発見が必ずあります。納得できるまで録って聴いてを繰り返し、フレーズごとにアプローチを調整しましょう。
ボイストレーナーに「どの表現が良いか」意見をもらうのも有効です。
まとめ
4つのステップはあくまでひとつの目安。曲によって流れは変わりますし、2周目・3周目でさらに表現を深めていくのも楽しいものです。
大切なのは、毎回の練習に“目的”を持つこと。その積み重ねが、声の安定と表現力を確実に育ててくれます。
「自分だけでは難しいかも…」と思ったら、ベリーメリーミュージックスクールの体験レッスンで、一緒にあなたの声の可能性を見つけましょう!
この記事を書いた人
大学在学中、大阪を中心として音楽活動開始。YAMAHA MUSICQUESTをはじめ、数多くのコンテストに合格。大阪でのインディーズCDリリースやバンド活動を経て2002年ACE OF HEARTS よりソロシンガーソングライターaoiとしてデビュー。